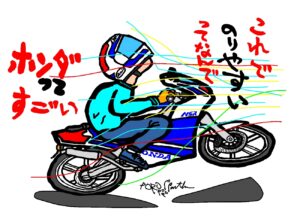皆さん、こんにちは。
先日、1月25日に一橋大学で経営学者として有名な野中郁次郎名誉教授が亡くなりました。旧日本軍が判断を誤り続けた要因を解明した84年の「失敗の本質」(共著)や日本企業の革新性の源泉を読み解いた95年の「知識創造企業」(同)などをご存知の方も多いと思います。
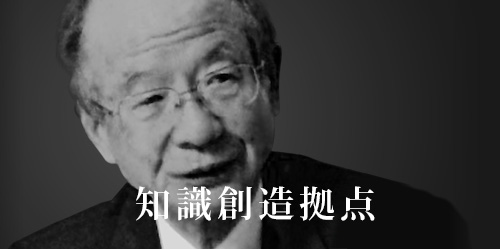
HP NIK – Nonaka Institute of Knowledge
2月1日付の朝日新聞のDeep Insightのコーナーに「「失敗の本質」野中氏の遺産」というコラムが掲載されていました。
野中さんは形から入り魂を入れない日本企業の根本的体質に警笛を鳴らされ続けてこられたそうです。その野中さんの心を打った経営者の一人が本田宗一郎さんだったようです。それは、米ミシガン州にある自動車殿堂で見た1枚の写真がきっかけになったようです。宗一郎さんがサーキット場で地面に顔をつけ、エンジンの響く音から車が思い通りの性能に仕上がったのかを見極めようとしている写真です。そして「これだ!」と思われたとのこと。人間には優れた暗黙知があり、それをどう組織で共有したらいいのか、の研究が始まったそうです。
ご覧になった写真はきっと以前の私のコラムでも紹介した写真と同じですね。やはり圧倒的に訴える力がある写真だったんでしょうね。

今こそ本田宗一郎~本田技研工業の創業者~ | Bikefun
そして提唱されたのがSECIモデルだったそうです。SECIモデルとは、個人に眠る暗黙知を集団で共有するプロセスのことです。さらに徹底した対話を経て暗黙知を言葉や論理により形式知に変換し、最終的には集団で獲得した知の実践を通じて個人の暗黙知をもう一段高めていく。PDCA(Plan Do Check Action)とは違う、共同化→表出化→連結化→内面化(4つも頭文字でSECI)という流れの繰り返しのことです。ホンダには社内で議論するときに「ワイガヤ」という文化がありますが、それがこのSECIモデルに近いらしいとのことでした。
その野中さんの著書の中に「本田宗一郎」(PHP、日本の実業家シリーズ)があります。サブタイトルが「夢を追い続けた知的バーバリアン」とあります。バーバリアン?日本語に訳すと野蛮人ということになります。野中さんから見た本田宗一郎を覗いてみましょう。
本田宗一郎とは何だったのか?
第二部に掲載さてれいる論考のタイトルです。どう御覧になったのでしょうか?
宗一郎さんは実践知リーダーで6つの能力に長けていたとのことです。
跳ぶ発想法
ある事実の観察から、それとはまったくことなる種類の、しばしば直接的
観察することが不可能な事実を推論する、拡張的かつ遡及的な発想方法だそうです。エピソードも沢山あります。
ハンマーで叩く音から車のボディの質の悪さを瞬間で見抜いたり、交差点で止まった隣の車のエンジン音がおかしいと言い出したところ、その言葉通り、エンジンが止まってしまった話、排気ガスの匂いでエンジンの好不調を言い当てた話など、全身これセンサーの方だったようです。
全身がセンサーのエンジニアの方は沢山いらっしゃいますね。
バイクの開発では、現在ではシミュレーションなど予測技術も進歩していますが、やはり最後は人が乗ってみて評価するかありません。
昔、トライアル車を開発した時のことでした。ご存知のようにトライアル車は人間でも登れないようなセクションを足を着かずに登っていきますが、それゆえにマシンを手足のように扱えることが要求されます。例えばスロットルを開けたときのドライバビリティも同じように開けたら同じように加速する必要があり非常に高い再現性が求められます。

ある時、トライアルライダーに開発中のマシンはドライバビリティの再現性が悪くて使えないと指摘されました。原因を突き詰める為に色々な計測を行いましたが原因究明ができませんでした。市販車の開発ライダーにも確認してもらいましたが、市販車レベルとしては問題ありませんでした。本当にダメなのか?半分疑いながら色々な測定を続けてもらいました。そうするとスロットルを開け始める一つ前の工程の混合気のA/F(空気と燃料の割合)がばらついていることに気が付きました。そしてそれを対策してもらって試乗してみてもらったところ、「これなら大丈夫!」とのコメントでした。
エンジニアとして疑ったことを恥じたとともに、まさに全身センサーの感度の高さに感服いたしました。
試す人になろう
また宗一郎さんは、実践を尊んだ人でもありました。「人生は見たり、聞いたり、試したりの三つの知恵でまとまっているが、その中で一番大切なのは試したりであると思う。ところが、世の中の技術屋というもの、見たり、聞いたりが多くて、試したりがほとんどない。」
「それは無理でしょう」「おそらく駄目でしょう」と言うと「やってみもせんで、何を言っとるか」と一括されてたそうです。エンジニア的には、やらなくてもわかることは、やらないほうがいいんですけどね(笑)。
実践を重んじるという点では三現主義、「現場、現物、現実」というものがあります。現場に行き、現物に触れ、現実を知り、判断し、動くということです。
バイクも世界中様々なところで販売されていますが、よく話題になるのが、「お前、行ったことはあるのか?」実際に行って、見てきた人には何を言っても敵わないのです。
ある年、アフリカ向けのモデルに携わっていたときにことでした。その当時は路面状況も整備されてなく、多人数乗りも多く、メンテナンスの環境もまだまだ不十分でした。そのような環境で本当に品質が保証できるのか?

現地のライダーはクラッチケーブルが切れても器用に操作し、ヘッドライトが壊れて天も向いていても平気なのだそうです。視力が良くて夜無灯火でも見えるのだとか。驚きです。
そこで夏休みを使って、ケニアとナイジェリアを市場調査に行ってきました。治安も悪く、移動する車の助手席にはライフルを持った警備員がいつも乗車しています。渋滞に差し掛かるとライフルを持ったまま窓から身を乗り出して、廻りの車を威嚇しながら進んでいくという初めての経験でした。
いずれにせよ現地に行くことで進めているプロジェクトに自信をもつことが出来ました。
また、乗車した車がディーゼル車で独特の排気ガスの匂いもきつく、夜ムカムカした中で夕食をとって部屋に戻ると、一気に気分が悪くなりトイレの便器を顔を突っ込んでいました。それは、忘れもしない56歳の誕生日でした、泣。
3現主義に加えて、5ゲン主義なるものもあります。現場、現物、現実の3現に原理・原則が加わります。基本的に、原理・原則に適っていないものはダメということですね。個人的にはこちらの方が好みです、笑。
フロシネスを備えた実践知りーダー
フロシネスとは、社会が奉じる「善いこと(共通善)」の実現に向かって、物事の複雑な関係性や文脈を配慮しながら、適時かつ適切な判断と行動をとることができる、身体性を伴った実践的な知性のことだそうです。
このフロシネスを糸口とし、古今東西、多くの優れた政治家や軍人、企業トップについて考察を深めた結果、実践知リーダーは次の6つの能力を備えていると考えるに至ったそうです。
1.「善い」目的をつくる能力
2.ありのままの現実を直観する能力
3.場をタイムリーにつくる能力
4.直観の本質を物語る能力
5.物語りを実現する政治力
6.実践知を組織する能力
終わりに
宗一郎さんを野中さんがどのように分析され、また具体的にどう実行されてきたのか?非常に興味深いですね。次回からさらにひも解いてみたいと思います。